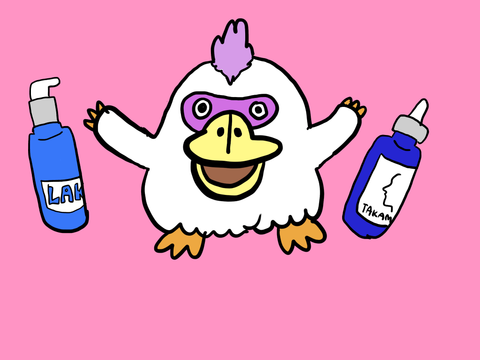©2011年映画「八日目の蝉」制作委員会
井上真央、永作博美が出演した「八日目の蝉」がAmazonプライム・ビデオの無料視聴対象になっていたので、先日、はじめてこの作品を観た。
真央ちゃんとナガサクさんはもちろんだけど、「伏兵」小池栄子の役どころと、その演技の良さにすごく驚いた。(小池栄子の役は、他人とのコミュニケーションが下手でちょっと電波系のいわゆる喪女だったんだけど、その表現がものすごく巧い。興味が出た方がいたら是非観てみてほしい)
おもしろかったので直後、図書館に行って原作の長編小説を借りた。
角田光代原作の単行本は人気が高すぎて数ヶ月先まで順番待ちだったので、視力の弱い方のために作られている「大活字版」を借りた。
大活字本を読むのは初めてだった。一つひとつの字がだいたい1㎝角くらいあって、行間も広いから、本が大きい。
長編とはいえ、文庫なら376ページで一冊に収まるくらいのお話だけど、こちらは2㎝あまりの厚みで3巻分のボリュームになる。

重いし、字が大きすぎると読みづらいだろうかと思ったが、なかなかどうして、わたしにはしっくり来た。
大きな文字の字間にも、指一本がおさまってしまうくらいの行間にも、単行本や文庫本を読んでいる時には見えない風景が見え、音が聞こえるような気がして驚いた。そしてその体験は、とても気持ちのよいものだった。
こういうサスペンス系のお話だと、わたしはどうにも、早くつづきが知りたくて気が急いてしまうところがある。
だからお部屋にどんな家具が置いてあるだとか、空にどんな雲が広がっているとか、人物が着ている洋服の模様がどんなだとか、そういう記述をけっこう豪快にすっ飛ばしてしまう。
文庫本だととくにそう。小さな文字で、駐車場に並ぶ車の車種だとか、お店で運ばれて来た飲み物がどんな色だとか、そういうこまごましたことが書き込んであると、それを目で拾うのも、文意を咀嚼するのもやめたくなってしまう。数行読んで、なまいきにもそれが物語の大勢にかかわりがないと判断したら、「もっと大味な」「もっと意味のある」言葉を探してわたしの視線は左へ左へ、急行してしまうのだ。
だけど大活字本だと、わたしはそういう強迫症めいた癖から解放されることができた。いつもは猛スピードで文字を呑み込んでは脳みそに送る作業をこなしているわたしの両眼も、脳内でそれらを瞬時に繋げて文章化し朗読している話者も、相手が大活字本になると、とたんに仕事が緩慢になった。
まるで絵本みたいに大きな文字で書かれた、短い1行を終えるごとに、わたしの眼も脳も呼吸も、なんだかとてもうっとりとして、満足そうに動きを休める。
視線がとまる、話者もとまる、風景がとまる。だからわたし自身も、ちゃんとその大きな1文字1文字に向かい合うことができた。
作者が、「他のどれでもなくこれを」と選んだ言葉、着せた洋服、降らせた雨。大きな文字の一つひとつが、ちょうどそれ一個分の重みをきっちりと伴って、わたしのところまでやってくるよろこび。
大活字になってはじめて、それぞれの要素は等身大の意義をもってそこにいることが叶っている気がした。彼らがなぜそこまで苦しまねばならなかったのか、3年半もの逃亡劇に果たしてどんな意味があったのか。それは、このだだっ広いザラ紙の平野にあってはじめて、余すことなく語られるような気がした。
1㎝角もある文字を20個つなげた1行を、字をおぼえたばかりの子どものようにゆっくりと辿ったら、隣に草むらのように広がる、1㎝弱の行間に腰をおろす。そうして今の1行がなんだったのかを、ちゃんと舌で触って、味がわかるまで噛んで、吞み込むことがようやくできる気がした。
そんなわけで秋の夜長に、長編小説の大活字本、学長はおススメです。寝そべっておふとんの中で読むときにも、目にやさしいよ。
(断じて 老眼では ない!!)
話は変わって、小説の映画化について勝手に語ります。
どのタイトルでも、「原作が良かったから映画化されたものを見たら、なんだかとてもがっかりした」みたいな話はよく聞きますよね。「八日目の蝉」も、人によってはそんな風に感じる作品の一つかもしれない。
思うに映画は、ものによって程度の差はあるけれど、最後には観客を「スッキリ」させてあげる役割を負っている。(フランス映画あたりはそうでもないけど)
たぶん漫画やゲームにも、だいたい同じことが言えると思う。冒頭で主人公が抱えていた問題を、がんばってがんばってついに万事解決、オメデトウハッピーエンディング!となるのがそれらの結末におけるセオリー。
単純に解決できないにしても、たとえばその人の成長をもって苦難を克服したり、誰かの助けを得て再生の道を歩み始めたり、ともかくなんらかの「大いなる救い」が結末までにかならず訪れるのが、映画とか漫画とかゲームのありようだと思う。
いっぽう小説は、悩める主人公を絶望と混乱のなかに放置することを厭わない。「人間って結局こうだよね、世の中ってひでえもんだよね。じゃ、がんばってね」って平気で幕を下ろす。
この差は「八日目の蝉」でも顕著で、映画と原作では、「何を見せようとしているか」にけっこう大きな違いがある。
「なぜ、私だったの?」
映画版ではキャッチコピーにもなっているこの言葉は、原作ではまったく違った意味あいで使われている。
「なぜ、私だったの?」
原作者の角田光代が主人公に語らせたこの言葉は、とても悲しくて普遍的な真実が込められていて、作品の核のひとつでもあると思う。
でもこのフレーズ、映画ではまったくべつの使われ方をしている。
原作者と映画制作サイドのあいだで解釈の対立があったとは、わたしは思わない。
ただ、小説と映画っていうのはそれぞれの立ち位置が違うのだ。
わたしたちはそのふたつを読んで、感じて、どちらでも自分になじむほうを自分のものにすればいい、ということなのだと思う。
ここまで書いてわたしは、いつものように唐突にドラクエの話に立ち戻るのだけれど、あっそーだ、マキさんいいこと思いついちゃった!
ドラクエ10の小説書いてみたいなー!って、今回思ったわけです。
小説ドラゴンクエスト。
ロトシリーズや天空シリーズをファンタジー作家の久美沙織さんが小説化した作品は、子どものころ単行本を買ってもらって、だいたい読みました。
いのまたむつみさんの麗しいイラストに惹かれて本を手にしたはいいけど、いざ読んでみるとけっこう難しい言葉が多くて、当時はあんまり内容を理解できなかったような気がします。

闘武群雄(小説ドラゴンクエストⅣ・1991年)
ドラクエⅣの小説はぜんぶで4巻あったのですが、それぞれの巻に、「双華流浪」とか「天空夢幻」とか、各章を象徴する壮麗な4文字熟語のタイトルがつけられていました。
これがすごくカッコいいなあと思って、同じような幻想的な響きを持つ4文字熟語を自分で考えては、画用紙に書いて机の前に貼って満足したりしていました。
あとですね、クリフトとアリーナがいろいろとムフフしちゃう、大人のシーンが出てくるんですよ。それでもうね、マキさんはどきどきして、机にむかって勉強するふりして、その部分を何度もこっそり読んだりしたことをよくおぼえています。
で、わたしがもしもドラクエ10のおはなしを書くならやっぱり、メインストーリーやサブクエストには描かれなかった、「行間」を埋めてみたいと思うのです。
たとえば、勇者アルヴァンと盟友カミルは世界を救いながらもバッドエンドにたどり着いてしまったわけですが、ふたりがその悲しい結末を迎える前は、どんな風にふたりで世界を旅していたのかが書きたい。
たぶんこれはちょっとした恋愛ものになるので、その路線でいけば、水の領界で出会ったフィナとヒューザの間にちょっとしたラヴ・アフェイアーがボッパツするやつとかも書いてみたいですね。
むふっ
いや書けるかわからんけど、言うは易し。
そういうのちょっとやってみたいなあなんてボケっと考えつつですね。少しずつ肌寒く、長くなってゆく秋の夜、マキさんはのんびりとたのしく、Ver4.3をやっているのでした。
[itemlink post_id=”1374″]
[itemlink post_id=”1375″]